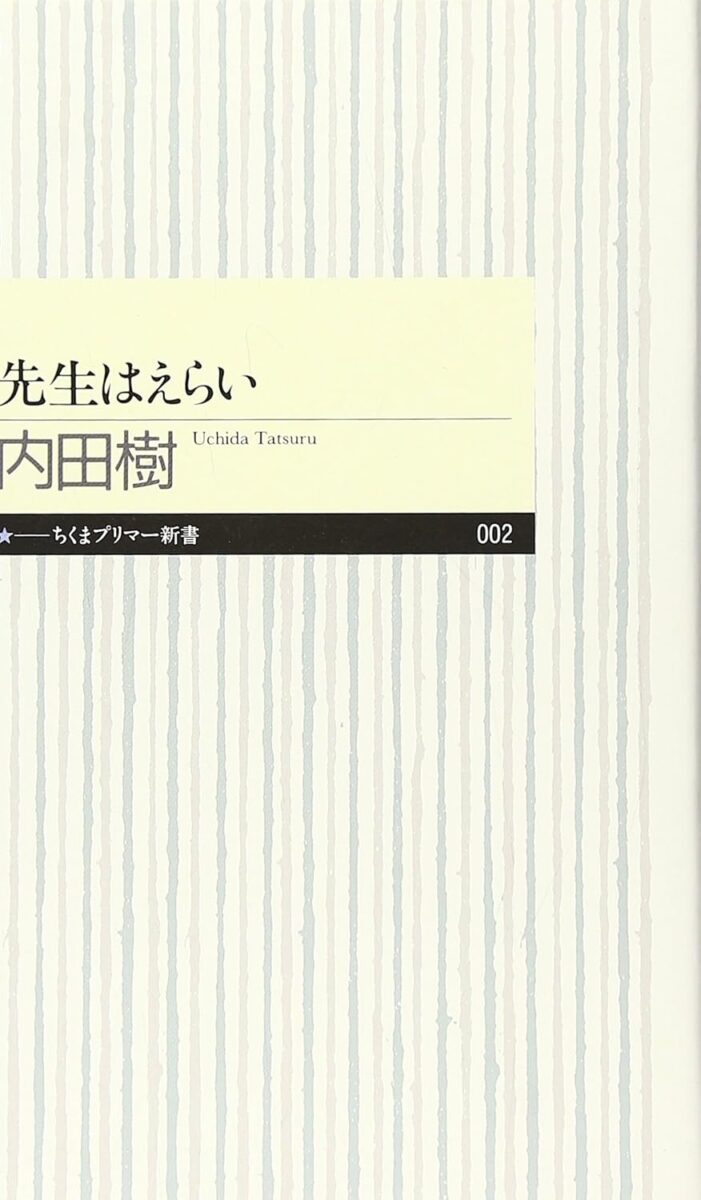

ちわわ、ちわ~!おいさんだよ!
キミは恩師と呼べるほどの先生に出会ったことはあるかい?
おい、『先生はえらい』って本?内田樹が書いたやつ。
なんか『何も教えてくれなくても先生はえらい』とか言ってるけど、なんなんだこりゃ?


ほほう、それは面白い話じゃ。
昔から『師の影を踏まず』という言葉があるが、それと似ておるかもしれんな。
でも実際、何も教えない先生ってなんだよ?
それじゃ教師失格だぜ?


ところがじゃ、その『誤解』こそが学びの始まりだと内田氏は言うておるのじゃ。
生徒が勝手に『この人はすごい』と思い込むことで、学びへの扉が開かれるという理屈なのじゃ。
はぁ?
そりゃどういうことだ?

\ ココがポイント!/

『先生はえらい』は、従来の教育観を根底から覆す革命的な一冊なのじゃ!
本書が提示する核心的主張は「先生は何も教えなくても、『えらい』と思われさえすれば学びの関係が成立する」という逆説的な理論である。
「先生はえらい」のです。たとえ何ひとつ教えてくれなくても。「えらい」と思いさえすれば学びの道はひらかれる。この一文に込められた思想は、現代の成果主義的教育システムへの痛烈な批判ともとれる。
内田の論理によれば、教育とは情報の一方向的伝達ではなく、学習者側の「誤解」と「憧憬」によって駆動されるコミュニケーション・システムなのだ。生徒が先生に対して抱く根拠のない「この人はすごい」という思い込みこそが、真の学びの出発点となる。
この理論は教育現場に大きな波紋を呼んだ。支持者は「学習者の主体性を重視した画期的な理論」と評価する一方、批判者からは「教師の責任放棄を正当化する危険思想」との声も上がっている。しかし、現代の教育問題─不登校、学級崩壊、教師のブラック労働─の根本原因を考える上で、本書が投げかけた問題提起は極めて重要かもしれない。
「えらい」教師って何?
本当は、先生のことを「偉い」だなんて思ったことはないのかもしれない。
理由は簡単、自分の人生の中であんまり良い先生に出会った試しがないからw

振り返ってみれば⋯⋯小・中・高と会ってきた教師はロクでもないものが多かったのう。
なんというか、どれもクセが強いものばかりでなんとも尊敬するに値しないクソ教師は常に一定の数おったものじゃ。
ああ、クセ強っていうか、クソ教師って一定の数必ずいるよなw
でも、まぁ学校なんてそんなもんだぜ。


今思うとそういうもんなのじゃが、それにしても聖職者と言われている教師があんなもんでいいのかと、当時は若気の至りながら大人にマジで反発していたものじゃ。
そういう意味で2本の教育は絶望的なのかもしれんのう。
そんなこんなであまり偉いと思う教師に出会わなかったわしは教師ガチャハズレ組なのか、学校教育を憎み、果ては教師を憎み、今ではこんな大人になってしまったw
そんなわしにこの本は意外な回答を与えてくれたような気がする。
「先生はえらい」?
今の日本の教育の現場に「偉い先生」なんて実際にどれだけいるのだろう?
そんなことを思いながら本書を読み進めていくと、別にそういう意味で書かれた本ではなく、学ぶ側の問題。
つまり先生と生徒。師と弟子の関係とはそもそもどういうものなのか?ということに焦点を当てつつ、現代教育の問題点をさらっていく⋯⋯そんな造りになっている。

読んでいて興味深かかったので、いくつか問題点をあげながら解説していこうw
感想
では、まず本書のあらすじを要約してみよう!
あらすじ
本書『先生はえらい』は神戸女学院大学名誉教授の内田樹が従来の教育論に一石を投じた問題作である。
全体は23章で構成され「恋愛と学び」「誤解のコミュニケーション」「沈黙交易」などのキーワードを軸に展開される。
著者は冒頭で「誰もが尊敬できる先生なんて存在しない」と断言する。そして恋愛関係を引き合いに出し、客観的評価とは無関係に「この人は特別だ」と感じる主観的体験こそが、師弟関係の本質だと主張する。
中盤では「教習所とF-1ドライバー」の比喩を用いて、技術的指導と真の教育の違いを論じる。単なる技能習得(教習所)と創造的学習(F-1)は本質的に異なり、後者においては学習者の主体的解釈が決定的役割を果たすとする。
特に注目すべきは「誤解のコミュニケーション」論である。
コミュニケーションは正確な情報伝達ではなく、受け手の創造的誤解によって成立するという逆説的主張を展開。『えらい』と誤解することで、えらさがわかるということだ。
終章では「沓を落とす人」のエピソードで、真の教師とは学習者に謎と憧れを与え続ける存在だと結論づけている。
まず最初に目を引いたのが「沈黙交易」という箇所。
交易が継続するためには、この代価でこの商品を購入したことに対する割り切れなさが残る必要があるのです。
クライアント「リピーター」にするためには、「良い品をどんどん安く」だけではダメなんです。「もう一度あの場所に行き、もう一度交換をしてみたい」と言う消費者の欲望に点火する、価格設定に関わる「謎」が必須なんです。
ふつうに考えると、相手の姿が見え、相手の言葉が理解できて、相手と価値観が共有できる人間と、その意味や価値が熟知されている財を交換することが「交易」であると言うことになります。
しかし、おそらく話は逆なのです。ここでも人間は原因と結果を取り違えています。姿が見えず、言葉がわからず、価値観が違う人間(だかなんだかわからないもの)とも、何かをやりとりすることができたと言うことの達成感が、交易を促した「最初の一撃」です。それによって得られた快感を求めて、もう何でもいいからじゃんじゃん交換しようと言うことで、その結果として、財としての使用価値のわかっているものも交換されるようになったと言うのが、ことの順序ではないかと私は思います。
P81・82
これは読んでいて膝を打ったというか、盲点を付かれたというか⋯⋯
商売において、良い品をどんどん安く提供すれば売上が上がって儲かる。そのような神話を素直に信じていたけれど、実はそれが相手と何かを交換する際に有効な手段なのではなく、「なんだかよくわからないもの」を相手に提供してまず相手の知的好奇心をくすぐり、長期にわたって相手と交易のパートナーシップを結ぶ、というのが長い目で見て大切なことである、という指摘はわし自身全く考えたこともなかった。
でも、考えてみたら当然である。
わしらは外国の物珍しいものとかを目にした時に(それが映画や音楽・謎の特産物や工芸品)、それが自分の理解を超えたものであるからこそ興味をそそられる。
そうした逆説的な状態を普段日常でよく目にするのだが、それをただボンヤリと当たり前と捉え、こうして深く考察するまでに至らなかった。
つまりこれは先生と生徒の間にも当てはまり、相手が一体何を持っているのか?こちらに何を与えてくれるのか?よくわからない状態というのが、「師と弟子」の関係に置いてはまずファーストステップとして重要なのだ。
問題になっているのは、いつでもコミュニケーションなのです。「話し合い」もコミュニケーションですし、「交易」もコミュニケーションです。
コミュニケーションと言うのは、要するに、何かと何かを取り替えることです。そして、沈黙交易のところで明らかになったように、何かと何かを取り替えたいと言う欲望が最も亢進するのは、そこで取り替えられるつつあるものの意味や価値がよくわからない時なのです。
だって、わかるとそれ以上コミュニケーションを続ける意欲を失われてしまいますからね。沈黙交易の場に、見慣れたものが置いてあったら、「なんだ、あれか」と思って、それ以上交易を続ける気分ではなくなりますからね。
人間同士のコミュニケーションはいつだってそうです。
P100・101

なんか先生のことよくわからんけど、この人についていけばわしの知らん「なんかすごいことを教えてもらえるんじゃないか?」とこっちが期待値を上げることが重要なんじゃな。
確かに相手がこちらの要求を超えるようなワクワク感を持ってないと人と付き合う意味はないもんな。

相手を否定し、拒絶するコミュニケーション
次に目を引いたのがこの一説。
聞き手に何の興味を示さないで熱く語り続ける語り手も、聞き手の存在を否定するメッセージを発信していると言う点においては変わりません。そういう人の話を聞かされると、私たちは弱い酸に侵されるように、深いところで傷つけられます。例えば、校長先生の朝礼の訓示とか、式典に来賓できている市会議員の挨拶みたいなものが、その典型です。そういうものを聞かされると人間は苦痛を感じます。
これは苦痛を感じるのが、人間として正しい反応なんです。
こういう話が私たちに苦痛を与えるのは、そこでもやはり「扉」が閉じられているからです。
「扉が閉じられた言葉」と言うのは、先ほども書いた通り、聞き手に向かって、「あなたはいなくても良い」と告げる言葉のことです。「あなたが私の話の内容を理解しようと理解しないと、あなたが言おうと今と、私は今と同じことを言うだろう」と告げられて傷つかない人はいません。
P113・114
「あなたはいなくてもよい」というコミュニケーション⋯⋯
こういうのする人ってたまにいますよねえ⋯

わしも大学に行った時に一人だけ、わしに対してこうした態度で接してきたヤツがいたのじゃ。
こちらは初対面で相手になんの思い入れもないし、何か相手の期限を損ねるようなことはしてないのに、今でも不思議に思うが何故相手はあんなふうな態度を取ってきたんだろう?
馬が合わないやつってのはどこにでもいるもんだ。
⋯⋯でもなあ、そういう奴に出会うとやっぱりこっちも傷つくのよなあw

教師の資格
漱石が先生の条件として挙げているのは、二つだけです。一つは「なんだかよくわからない人」であること、一つは「ある種の満たされなさ」に取り付かれた人であること、この二つです。
「先生」が「なんだかよくわからない人」になってしまったことの原因が「先生」が「ある種の満たされなさに取り憑かれた」ことにあるのだとすると、これは同じ一つの経験の前後二つの相と申し上げてよいのかもしれません。だどすると、一つですね。
漱石はそう書いている以上、「先生」が「先生」として機能するためには、これだけで充分ということなのでしょう、きっと。
P146・147
この「なんだがよくわからない人」というのがおもしろい。
一見、ふざけてんのか?と思うかもしれないが、なにか「よくわからない」ということは、こちらが知らない何かを知っている人であるという可能性が高いということである。
ならば、そうした人から自分の知らなかった何かを、自分が知覚し得なかった世界を教えてもらえるということでもあるのだから、そうした人との関係は大切にしたほうが良い。もしかしたら自分の狭い世界を変えてくれる相手かもしれないからだ。

わしも思い返せば、高校時代に出会ったわけわからん友人に、自分が閉じこもっていた狭い世界を壊してもらったもんなあ⋯⋯
思えばアレは強烈な体験じゃったw
そんな相手に出会えるってのも幸運な体験だよなw


ただその時はそれなりに痛みを伴う経験ではあったんだけどなw
コミュニケーションにおいて正解と言うものが認められると、コミュニケーションの受信者は1人で良いと言うことになり、それ以外の人々はコミュニケーションの場から速やかに退去せよと言うことになります。
それでは困ります。
人間の定義は「コミュニケーションするもの」と言うことです。つまり、「コミュニケーションしない人間」は人間じゃないと言うことです。コミュニケーションにおいて「正解」と言うものを求めてしまうと、ほとんどの人間はその存在理由を失って、人間じゃなくなってしまいます。
人間と言うのは、言い換えれば「誤答者としての独創性」です。あるメッセージを他の誰もそんなふうに誤解しないような仕方で誤解したと言う事実が、受信者の独創性とアイデンティティをつけるのです。
1人の師に複数の弟子がいて、弟子たちは全員が師の蔵する「謎」の解読に失敗します。失敗することが義務付けられているのです。でも、正しく全員が師の「謎」を解くことに失敗するおかげで、弟子全員が師との対話を(師の死後でさえ)続け、弟子同士で「ああでもないこうでもない」と「謎」について終わりなく議論し合うことができるのです。そんなふうにして一人ひとりの弟子のアイデンティティーと主体性を基礎づけられているのです。
すべての弟子や私を理解することに失敗します。けれども、その失敗の仕方の独創性において、他のどの弟子によっても代替できないかけがえのない存在として、師弟関係の系譜に名前を残すことになります。
(中略)
別に「大人」になったからといって、いきなり賢くなるとか、世の中の仕組みが洞察できるようになるとかと言う事はありません。
とりあえずわかるのは自分の馬鹿さ加減だけです。
でも、それに気づいて、「あぁ、そうか俺のアイデンティティというか、余人を持っては代替不能であるところの「かけがえのなさ」と言うのは、まさに俺の「バカさ加減」によって担保されているわけだ……」という冷厳なる事実の前に粛然と襟を正しているうちに、青年活気でブイブイを合わせていた頃に比べると、なんとなく腑抜けたような「おじさん」ぽい顔つきになるわけです。
P150・151 152

これも読んでいて衝撃的だったというか⋯⋯
確かに長いこと生きてきてわしがわかったのは、自分が以下に至らない「ポンコツであるか」ということに気づいたということなのじゃ。
ようやく悟りの境地に至ったのかw
⋯遅かったなw


うるさいわい!
そうしたことに気づけたということが、本人にとっての成長なのじゃ!
良いところ
では以下に良い点を挙げていこう!
学習者の主体性を最重視する革新的視点
内田樹の最大の功績は、教育における学習者の主体性を理論的に基礎づけた点である。
従来の教育論は「いかに効率よく知識を伝達するか」という教師中心の発想に支配されてきた。しかし内田は「学ぶ」という行為の本質が学習者側(生徒)の能動的解釈にあることを明確に示した。
あなたが「えらい」と思った人、それが「あなたの先生」なのだ。この洞察は深い。教育の成否を決めるのは教師の技量ではなく、学習者がその関係をどう意味づけるかなのだ。この視点は現代の画一的教育システムに対する強力なアンチテーゼとなっている。
また「誤解のコミュニケーション」論は、学習における創造性の重要性を浮き彫りにする。正確な理解ではなく、学習者なりの解釈こそが新たな知見を生み出すという主張は、現代のクリエイティブ教育論の先駆けとも言える。
恋愛論との巧妙なアナロジー
内田の議論で特に秀逸なのは、師弟関係を恋愛関係のアナロジーで説明した点だ。
この比喩は単なるレトリックではなく、人間の認知メカニズムの本質を突いている。
恋愛においては客観的評価は二の次で、「この人は特別だ」という主観的確信が全てを決定する。同様に教育関係においても、「この先生はすごい人だ」という学習者の思い込みが学習動機の源泉となる。この構造的類似性の指摘は見事だ。
さらにこの比喩は、なぜ「万人にとって良い先生」が存在し得ないかを明快に説明する。恋愛に「万人にとって理想的な恋人」がいないのと同様、教育にも「万人にとって理想的な教師」は存在しない。個別性と主観性こそが本質なのである。
現代教育問題への鋭い診断
本書は2005年の出版だが、現在の教育現場が直面する諸問題を予見的に診断している点で評価が高い。
不登校や学級崩壊、教師の疲弊などはすべて「客観的で効率的な教育」を追求した結果として理解できる。
内田が提示する「沈黙交易」のモデルは、現代の過度なコミュニケーション重視への批判として読める。何でも言語化し、明示的に伝達しようとする現代教育の病理を、見事に喝破している。
内田樹さんという人は評価が難しいとされる。ネットスラングで言うならば「香ばしい」人扱いされることもあるし、一方では著名な思想家として扱われることもある。賛否両論はあるものの、本書が教育現場に与えたインパクトは計り知れない。

まぁ読んでいる人の好き嫌いはあるかもしれないが、書いてあることは至極全うで読んでいてハタと膝を打ちたくなることが満載だから読んで損はない一冊じゃ。
何かあるか?
まぁページ数も短いし、論旨もコンパクトに纏まっているから、読んでいて苦痛はないぜ。
いいんじゃね?

気になった方はこちらからどうぞ
悪いところ
では以下に悪い点を挙げていこう。
理論の実用性に欠ける
内田の教育論は哲学的洞察に富む一方で、実際の教育現場での応用可能性に乏しい。「誤解を大切にせよ」「沈黙を重んじよ」といった提言は美しく聞こえるが、具体的な教育実践に落とし込むのは困難かもしれない。特に現代の成果主義的教育システムの中で、どう実現するかの道筋が示されていない。
教師の責任軽視の危険性
「何も教えなくても先生はえらい」という主張は、教師の職業的責任を軽視する危険性を孕む。確かに過度な教授主義は問題だが、教師には専門知識を適切に伝達する責務がある。内田の論理を拡大解釈すれば、教師の怠慢を正当化する口実に使われかねない。
エリート主義的偏向
内田の議論は知的エリート層の体験を基盤としており、一般的な学習者の実態から乖離している面がある。神戸女学院大学という私立女子大での経験が色濃く反映されており、公教育の現実的課題─基礎学力の定着、進路保障など─への視点が欠けている。理想論に偏りすぎて、現実的な教育問題への処方箋として機能しにくい。

あんまりいないと思うけど、これを読んで現代の教育を変えようと思っている人はあんまり意味はないと思うな。
まぁ自身の教育観を問い質せって趣旨だとオレは思うぜ。
あんまり現代の義務教育とかに過度な期待は厳禁だよな。


話半分で聞いておけばいいのじゃ。
まとめ
こんな人におすすめ!
- 教育関係者で従来の指導法に疑問を感じている人 - 画一的な教育システムへの違和感を理論的に整理できる
- 子育て中の親で「教えすぎ」を反省したい人 - 子どもの主体性を尊重する育児のヒントが得られる
- 哲学的思考を好む読書家 - 教育という身近なテーマを深く考察する知的刺激が味わえる
『先生はえらい』は、教育の本質を「情報伝達」から「関係性の構築」へとパラダイム転換を促した画期的作品である。内田樹の提示する「誤解のコミュニケーション」論は、現代教育の客観主義・効率主義への痛烈な批判となっている。
本書の最大の価値は、学習者の主体性を理論的に基礎づけた点にある。教育の成否は教師の技量ではなく、学習者がその関係をどう意味づけるかで決まるという洞察は、現代の教育問題を考える上で極めて重要だ。
ただし理論の実用性や教師責任論への配慮不足など、批判すべき点も多い。特に公教育の現実的課題への視点が欠けている点は大きな限界と言える。
それでも本書が提起した問題意識─画一的教育システムの弊害、学習者の個別性の重要性─は、20年近く経った今でも色褪せない。現代の教育現場が直面する不登校問題や教師の疲弊を理解する上で、内田の診断は今なお有効である。
賛否両論を呼ぶ問題作だが、教育に関わる全ての人が一度は読むべき必読書といえよう。

教育とは、人と人との間に生まれる不思議な化学反応なのじゃ。
どんなに制度やシステムを整えても、その瞬間の魔法は計画できん。
内田樹はその魔法の正体を見事に言い当てたのじゃ。







