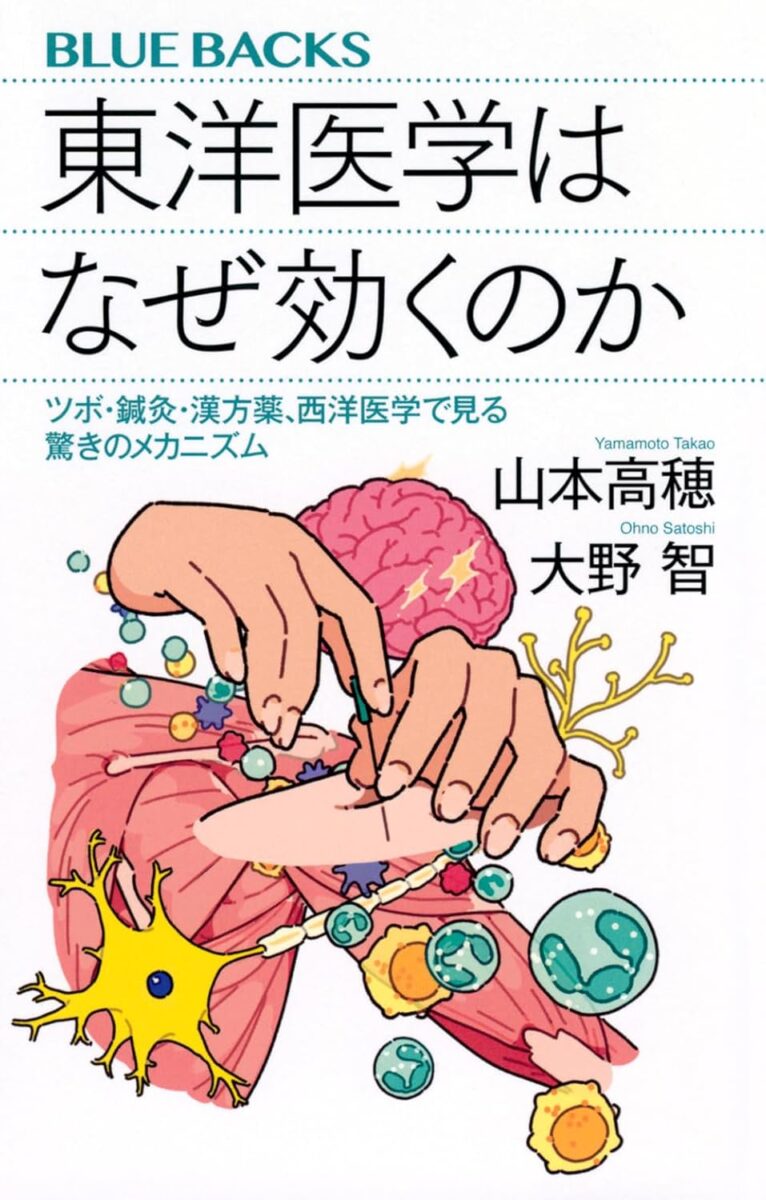

ちわわ、ちわ~!おいさんだよ!
東洋医学を信じているかい?
東洋医学って、ホントに効くのか?


いやいや、これがなかなか効くものなのか?
だって、経絡とかツボとか科学的に証明されてないじゃん


『東洋医学はなぜ効くのか?』を読んでみると良いのじゃ。
現代科学と折り合いをつけながら、東洋の知恵を解き明かしておる本なんじゃぞい
へぇ、ブルーバックスか。
それなら、なかなか参考になりそうだぜ。

\ ココがポイント!/

『東洋医学はなぜ効くのか?』は、現代の科学的視点から東洋医学の仕組みを解析し、その有効性を論理的に解き明かそうとする一冊なのじゃ!
著者は「東洋医学=非科学」という偏見に対し、気・経絡・体質診断といった概念を、生理学・免疫学・神経科学といった最新の知見をもとに再評価する。科学と東洋思想の融合を志向する姿勢は、単なる代替医療の解説にとどまらず、現代医療の限界を浮き彫りにする。本書の価値は「なぜ効くのか?」という問いに真摯に向き合い、曖昧な概念を検証しようとする姿勢にある。代替医療に懐疑的な読者であっても一読の価値があるだろう。
導入(冒頭でズバッと)
ずっと長いこと腰痛を患っていた。
随分昔の話である。
21歳の頃、吾輩は故郷を離れ、母方の実家である宮崎にいた。
そこで祖父母の介護の手伝いをしつつ、晴耕雨読の日々を送っていた。
しかし、そんな生活を続けていたら体が鈍ってしまう。
そこで慣れない筋トレを始めることにした。

それが今思えば命取りだったのじゃ。
それで筋トレ中に腰を痛めたんだっけ?

思わぬ腰痛に日々の暮らしもままならぬほどの痛みに苛まれる日々。
当時ひとり暮らししていた神奈川に戻ってから、近くの整体に通うも一向に良くならず⋯⋯
腰痛を患ってからもうすでに4年も経っていた、そんな日々を送っていた内にある一冊の本に出会った。

それが永井峻先生の本だったのじゃ
そのおかげで腰痛はほぼ完治しているのじゃ。
よく考えてみたらそれは東洋医学をベースにした治療方法であった。
しかし、そんな自身の腰痛改善の体験を経て、ある疑問が沸き起こった。
東洋医学ってなぜ効くのだろうか?というものである。

正直、ツボとか経絡とか言われてもピンとはこないのじゃ。
そこで本書を読んで東洋医学がなぜ効くのか?そのメカニズムを西洋医学の観点から観察してみたのじゃ!
感想
あらすじ
本書は、「なぜ東洋医学が効くのか?」という疑問を科学的に紐解くことを目的としている。
東洋医学では病気を“全体”として捉える視点が特徴であり、「気」「経絡」「陰陽」などの概念が用いられる。一方、著者はこれらの考え方を、現代科学の言語で読み替える。たとえば、経絡は神経系のネットワークに、気はホメオスタシス(恒常性維持機能)と自律神経の働きに置き換えられうると論じる。また、鍼灸や漢方が人体に与える影響を、脳波や免疫応答などのデータと照らし合わせて検証していく。さらに東洋医学の診断技法が「主観」と見なされがちな点についても、心理学や脳科学の観点から再定義を試みており、科学と伝統の対話を促す内容となっている。
読んでみるとさすがにブルーバックス。
高校生でも内容を理解できるように作られているだけあって、とてもわかりやすい内容で書かれている。
従来効くとされているツボや経絡は西洋医学の視点で詳細に解明する試みがなされてきた。
その結果、最近の研究ではツボや経絡と呼ばれる場所は神経で脳と密接につながっていることがわかり、経絡とは痛みが集中するトリガーポイントなのではないだろうか?という指摘がなされている。
トリガーポイントとは具体的に言うと「痛みの引き金となる点」と呼ばれていて、別名、圧痛点とも呼ばれている。
そして驚くべきことにアスリートを使った痛みの場所を特定しマーキングする手法で比較したところ、このトリガーポイントがツボ周辺に集中していることがわかってきたのである。
つまり体のコリ=トリガーポイント
経絡とはそのトリガーポイントに刺激を与え、コリを解消する場所ということである。

そうしたことが近年の研究の成果によって徐々に解明されてきたのじゃ。
へぇ〜、つまり体のコリっていうのは、いわゆるツボと呼ばれる場所に集中する傾向があって、それが経絡と呼ばれるトリガーポイント=痛みの場所とかぶるってことがわかり始めたのか。

そして鍼治療とはこの経絡の場所を、針によって痛みをコントロールする技術であるということもわかってきたという。
体に張り巡らされた神経の束は全て背骨を通って脳とつながっている。
従来の整体や鍼灸師はその経絡を揉んだり、針で刺激することによって、血行を促し痛みを緩和する技術を積み上げてきたのである。
しかしなあ。
そうは言っても鍼治療なんか効くヤツと効かないヤツがいるだろ?
単なる思い込み、もしくは偶然なんてケースもあるんじゃないか?


鋭い指摘じゃ!
そのとおり、医学は時に思い込みによって作用するプラセボ効果というものがある。
その点は東洋医学も例に漏れないのじゃ。そこで気をつけるのがサンタ論法。
サンタぁ?


サンタクロース村が来るの?
サンタ論法の戒めと科学的根拠
(前略)
患者の診療に携わる臨床医の視点からすると「針を打った→頭痛が改善した→だから、針は効いた」と言うロジックは「サンタ論法(3つの文の末尾が他で終わるため3つの「た」=サンタ)と呼ばれ、治療の効果を単純化しすぎないための戒めとなっています。
ある薬を飲んで病気が治ったとしても、他の要因が影響していないか、薬を飲まなかったとしても治ったのではないかなど、薬以外の可能性を色々と考える必要があるのです。
P222

このように針を打ったから症状が改善した。漢方を飲んだから体調が良くなった。
…というのは単純すぎる。そこで西洋医学ではある治療法・医薬品が実際に効くのかどうかを知るためにはランダム化比較試験というものをしなくてはいけないのじゃ!
なんだよ、そのランダム化比較試験って?

ランダム化比較試験
ランダム化比較試験とは次のような実験方法である。
(中略)
そのため、医学的に「〇〇に効く」と主張するためには、ランダム化比較試験で有効性が証明されていることが重要になってきます。ではランダム化比較試験とは何でしょうか。
具体的には、臨床試験に参加する対象者をランダムに分けて、それぞれに評価したい治療法と別の治療法を行って比較する方法を指します。対象者をランダムに分けることで、検証したい治療法以外の要因がバランスよく分かれるため、公平に比較することができるのが特徴です。
なお、ランダム化比較試験では、対象者(患者)も医師も振り分けられるグループを選ぶことはできません。そのため、無作為化比較試験とも呼ばれています。
(中略)
医学・医療の領域で、治療法が客観的に「効く」と主張するためにはランダム化比較試験で検証し有効性が示されていることが重要です。裏を返せば、ランダム化比較試験で有効性が証明されていれば、その治療法は「効く」と言えるのです。そして、この考え方は、鍼灸、漢方薬であっても同じで同じです。さらに日本に限った話ではなく世界共通のものです。また、現在は薬事承認の手続きにおいても、薬の候補となる物質が厚生労働省に薬品として認められるためには、原則としてランダム化比較試験で検証することが求められます。
P225・226
つまりある医薬品が実際に効くのかを調べるためには被験者を無作為抽出で集め、それぞれに医薬品を飲んだグループと飲んでないグループに分けて、その医薬品がどのような効果をもたらしたのかを長期間調べつづける手法がランダム化比較試験である。

鍼灸の場合では「針を打ったグループ」と「打ってないグループ」にそれぞれわけるのは元より、お前のように「東洋医学なんて嘘だろ?」と思い込んでいる人間もそろぞれのグループに分けて配置しなければならない。もちろんどちらかのグループに多めに配置してなんてなことがないように、無作為に選ばなければならないのじゃがなw
なるほど、思い込みとかで効果が変わったりすることが実際にあるから、東洋医学を信じている人も信じていない人も両方ランダムで比較して効果・効能を計測するってわけか。
こりゃ納得だわ!

ただし、ここで知って欲しい置いて欲しいことがあります。
ランダム化比較試験で有効性が証明されれば、その治療法は医学的に「効く」と言うことができます。ですが、その「効く」はずの治療法を受けても、全員の病気が治ったり、症状が改善したりするわけではありません。これを医療の不確実性といいます。今後、例え医学が進歩したとしても医療の不確実性はついて回ります。
つまり、臨床試験の結果は「全く効かない、全員に効く」といった白黒をつくようなものではなく「どれぐらいの割合の人にどれくらい効くのか」と言うことを示すものなのです。
(中略)
ここまでの説明を整理するポイントは2つです。
- 治療法が医学的に「効く」と言えるためにはランダム化比較試験で有効性が証明されていることが重要
- ただし、ランダム化比較試験の結果には「医療の不確実性」が伴い、「効く」ことが証明された治療法を行っても全員が治るわけではない。

あ、ただし漢方に限ってはその独特の味と匂いが影響して、同じ味・匂いのする偽薬を作るのが困難な状況なのでプラセボ効果を計るのが難しい場合があるという点があるようじゃ。
まぁ漢方って独特な苦みとか匂いとかあるもんな。
見た目と味と匂いで見破られたら偽薬の意味がないぜ。


そして近年ではそうしたランダム化比較試験の結果、東洋医学は腰の痛みやうつの改善など諸々の症状に実際に効果があると認められる論文が数多く輩出しているようじゃ。
つまりわしらが昔から身近に触れていた鍼灸や漢方などの医療行為は21世紀の現代でも友好であるということが証明されつつあるのじゃな。
良いところ
では以下に良い点を挙げていこう!
科学と伝統の橋渡しを試みている
東洋医学の概念をそのまま受け入れるのではなく、科学的な知見に照らして再定義していく姿勢は誠実である。
「気」や「経絡」といった曖昧に思われがちな概念が神経や免疫系との関係で語られることで、読者は「東洋医学=非科学」という誤解から一歩踏み出すことができる。
最新の研究やデータを丁寧に紹介
本書では脳科学・自律神経・ストレス反応など、現代医学の知見が豊富に紹介されている。
特に「鍼灸治療によって脳の血流が変化する」といった具体的な実験結果が示されており、信頼性が高い。科学的裏付けに基づく考察が、説得力を生み出している。
誰にでも読みやすい構成
ブルーバックスらしく、難解な東洋思想や生理学も平易な言葉で解説されている。
専門用語が出てきても必ずと言ってよいほど図解やたとえ話で補足されるため、医療の知識がない読者にも理解しやすい。導入から結論にかけての流れも明快であり、スムーズに読了できるだろう。

やはり医学について書かれた本じゃから多少難解な言葉は出てくるが、それでも最後まで割と読ませてしまう内容が書かれているのじゃ
難しい医学用語や漢方の種類なんかの記載はあるけど、我慢して最後まで読むことはできるよな。
良い本だぜ。

気になった方はこちらからどうぞ
悪いところ
では以下に悪い点を挙げていこう。
科学的根拠がまだ曖昧な部分もある
「経絡=神経系のネットワーク」という説には興味深さがあるが、すべての仮説が厳密な実証を伴っているわけではない。よって、科学的に説得されるには一歩及ばない部分も残されている。
西洋医学との比較がやや一面的
東洋医学を持ち上げる一方で、西洋医学の限界を過度に強調しすぎている部分がある。読者によってはバランスを欠いた印象を受けるかもしれない。
経験者目線のエピソードが乏しい
理論や研究紹介に重点が置かれており、東洋医学を実際に受けた患者の声や現場のリアルな描写が少ない。体験ベースの説得力がもう少しあれば、読者の共感を呼びやすかっただろう。

少し経験者の声が少ないカンジがしたが、でもまあブルーバックスなので普通の健康法を記した健康本ではないのでこれくらいなら妥当なんじゃないかな?
セルフケアの本は自分に都合の良い点しか書かないからな。
その点でこの本は科学の視点で現代の東洋医学の構造を解き明かしている気がするぜ。


すごく目からウロコの良い視点が満載の本なのじゃ!
まとめ
こんな人におすすめ!
- 東洋医学に興味があるが、根拠が知りたい人
- 科学的な思考で健康を考えたい人
- 医療や健康に関心があり、別視点を学びたい人
『東洋医学はなぜ効くのか?』は、東洋医学をただの伝統として扱うのではなく、現代科学の視点からそのメカニズムを解明しようとする意欲的な試みである。著者は、「気」や「経絡」といった概念を曖昧なまま放置せず、それらを生理学的・神経学的観点から読み解くことで、東洋と西洋の架け橋を築こうとする。理論的な裏付けや研究事例の紹介も豊富であり、読み応えは十分。伝統医療を批判でも称賛でもなく、「理解する」ための手がかりを与える本書は、医療に関心をもつすべての読者にとって価値ある一冊である。

東洋医学を“オカルト”と決めつける前に、一度は科学の目で覗いてみるがよい。
案外、西洋より理に適っておる部分も多いものなのじゃ──読めば身体の声が聞こえてくるやもしれんのじゃ!







