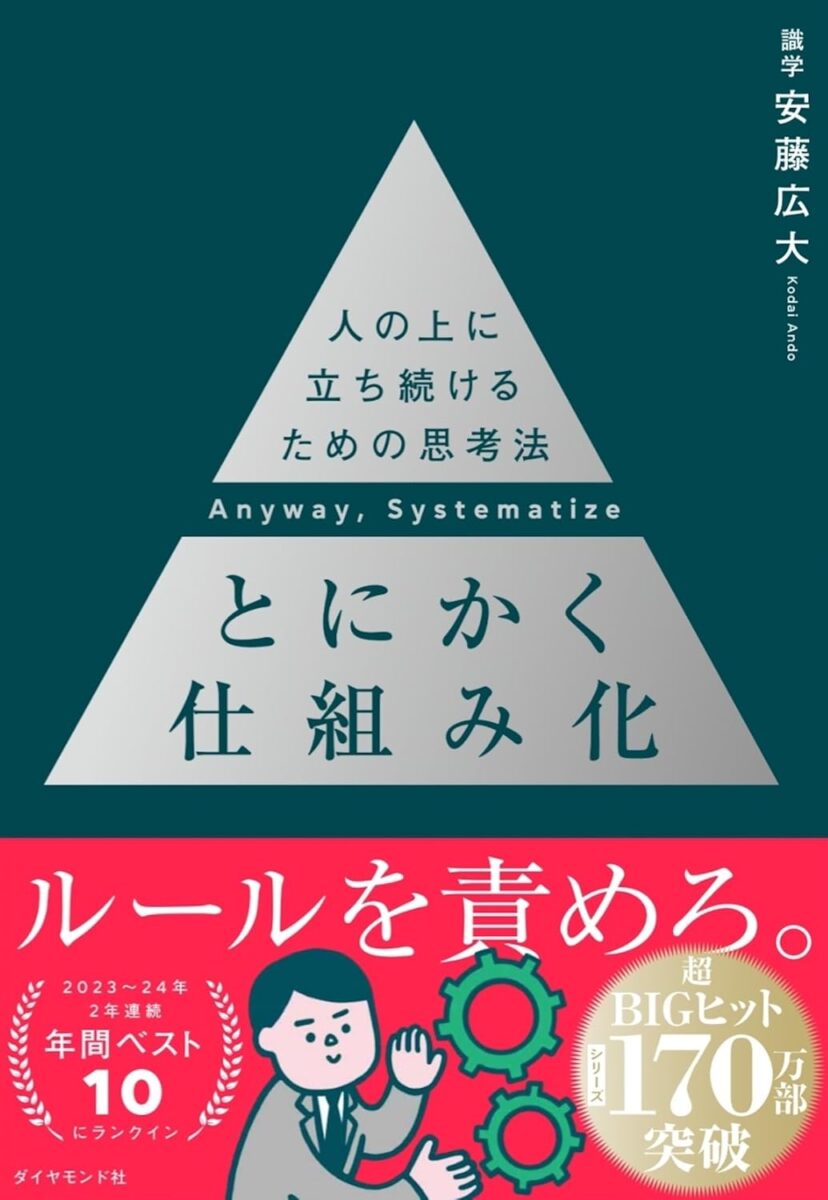

ちわわ、ちわ~!おいさんだよ!
キミは組織に身を置いたことはあるかい?
組織って、会社のことか?
お前、組織で働いたことはないだろ。
「仕組み化」って言うけど、本当に効果あんのか?


会社に就職したことはないが、バイトで組織の一員になったことはある。
本書は3500社以上に識学を導入した実績が方法を綴った本なのじゃ。
へぇ、そんなに広がってんのか。内容がわかりやすいとかで?


非常にシンプルで読みやすい言葉で整理されておるし、何よりもわかりやすいのじゃ。
属人化を防いで組織を強くする、とにかく仕組み化…興味湧くぜw

\ ココがポイント!/

結論として、『とにかく仕組み化』は、組織で変革を目指すリーダーや管理職にとって必携の一冊なのじゃ!
3500社以上に導入された識学メソッドに基づき、「人ではなくルールで問題を解決する」思考を伝授する点に本書の強みがあるnote(ノート)紀伊國屋書店。
発売から1ヶ月で22万部突破という驚異的な部数は、ビジネスパーソンからの共感の証だAudible.co.jp。実際、シリーズ累計100万部を超える人気シリーズの完結編に相応しい完成度であり、統一された思考の流れにより、読者は「仕組みで人を動かす」の本質を感じ取れるだろうプレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES。ただし、哲学的な深掘りを望む層にはやや平易と映る傾向もある。
だが、実践的な組織運営を目指すなら、即効性のある思考法として重宝するだろう。
仕組みで組織が変わる?
今の今まで組織の一員になったことはない。
というか、就職したことはない。いつまでもフリーランスとしてこれまでずっと生きてきた。
しかし、過去にはバイト先で組織の一員になったことはある。
その時はなぜ、こんなつまらないルールがあるんだろう?
なぜ、こんなに不便としか思えない取り決めがあるんだろう?
と組織が押し付けてくる規制(レギュレーション)にいつも首をかしげていた。そしていつも不満を持っていた。
こうしたものは個人の実力を削ぐものであり、あまりルールで縛らない方がうまくいくのではないだろうか?⋯と。
しかし、本書を読んでその思いが少し揺らいだ気がする。何しろ吾輩がバイトをしていたのはだいぶ前の話だ。昔の思い出など、とうに記憶が風化しているから、当時抱えていた組織が規定したルールへの反発心は、どことなく薄い印象しか残っていないとしか言えない。

吾輩は学生時代には漫画喫茶でバイトした経験があるけど、その時は「アレをするな、これをやれ」と規制だらけでウンザリしたものじゃ。
100円ショップでも働いてたよな。
日本はマニュアル社会って言われているから、いろんなことがマニュアルにされていて、色々細かい規定があって面倒くさいと思うぜ。


働いていた時はそれが嫌で嫌でしょうがなかったけど、今考えるとそうした考えは間違っていたのかなあ?
本書はそうした組織の「属人化を防いで、個人では成し遂げられない大きな目標を達成する」ための考え方を綴った本なのじゃ。
感想
「とにかく仕組み化」の要約はこんなかんじ。
あらすじ
本書『とにかく仕組み化』は、著者・安藤広大が提唱する「識学」の集大成とも言えるビジネス書である。
そもそも識学は個人の属人化を防ぎ組織全体を効率的に機能させるメソッドであり、本書ではそれを「仕組み化」という形で具体的に紹介している(note(ノート)紀伊國屋書店)。全体を通して、「責任と権限の明文化」「仕組みを変える覚悟」「誰にでも公平な組織」「企業理念の浸透」「進行感のある運営」といった章立てで、組織の基盤を強くするための思考法が整理されている(紀伊國屋書店kt-kiyoshi.comnote(ノート))。
手間を減らし、再現性のあるマネジメントを構築したい管理職には、即効性のある指針が詰まっている内容である。
普段わしらが生きていると誰しも「かけがえのない人」になりたいと思うことが多いだろう。
特にクリエイターみたいな仕事をしている人は特にそんな傾向が強いかもしれない。
しかし本書はそんな傾向に警鐘を鳴らす。
掛け替えのない「カリスマ」よりも誰とでも代われる「歯車」になる。
そうした人生を推奨しているのだ。
どういうことだよ?


ふむ、以下に本書からの抜粋を見てみるのじゃ。
替えの効かない人になりたい欲望
「かけがえのない人になりたい」
「歯車ではなく、買いのきかない人になりたい」
そんな欲望が、人間にはあるはずです。その翼の存在を否定しません。
「あなたがいないと困るんだ」と言われて、嫌になる人はいないからです。ただ本音と建前があると思うのです。
トッププレイヤーで社員の引き抜かれて、その会社が絶望に刺されるとしましょう。最初は「あなたがいないと困る」と言って引き留めるでしょう。しかし、人の上に立つ人は、残された面を信じないといけません。
「一時的にピンチですしかしこのメンバーなら大丈夫です」と言うことを伝えるのです。すると、思いもよらなかった社員が代わりにエス級の活躍をするようになります。そうやって人の成長を信じ入れ替わりが起こるのが「良い組織」です。仕組みがあればピンチを救えます。さらに、そのピンチを乗り越えると、組織が脱皮して大きくなります。そうやって、より強固な体質になっていく会社を、私は数多く見てきました。
だから、「組織の中で替えが効くようにしておく」と言う人が逆説的に優秀なのです。型にはまった人が、やがて大きく化けます。
そのためにも「仕組み化」が根底に必要になってくるのです。
P23・24
組織を運営するうえで1番恐ろしいことが誰かに権限が集中する「属人化」。
それを人間が体現する「カリスマ」という存在は創業時には非常に有効な駆動力になるかもしれないが、代替わりの際にはその「属人化」によるしっぺ返しを喰らいがちである。
それで代替わりの際に後継者選びに失敗して会社が傾くなんて話は枚挙に暇がないもんな。


そうじゃ。カリスマ経営者で成り上がって一声を風靡した「ダイエー」しかり「ヤオハン」しかり⋯⋯
今では「ヤマダ電機」とか「ユニクロ」とか「イーロン・マスク」とかもその傾向が強いから、もしかしたら創業者が去った後は危ないかもしれないのう。
属人化ほど怖いものはない。
仕組み化の反対は「属人化」です。
属人化とは、その人にしかできない業務が存在してしまっている状態です。例えば、仕事ができる人は「できない人」の気持ちがわかりません。何を隠そう、昔の私はそのタイプでした。識学を知る前までは、「部下側の能力」に問題があり、「会社側の仕組み」に原因はないと思い込んでいました。
しかし、チームのメンバーが成長しなかったのは、組織を運営している管理職や経営者に100%責任があると言う事実に気づいてしまったのです。もちろん、それまでの私は、部下の成長をやめようと思って日々を過ごしたわけではありません。
自分なりに必死で、部下にも成長してほしいと思い、良かれと信じていた行動が間違っていたのです。
P56
そうした創業者一族亡き後も会社を存続させる道がいわゆる「仕組み化」にあると本書の著者は主張する。
そしてその際に大事なのはやはり社内に蔓延る権力の使い方、いや権力のコントロールの仕方である。
権力は使い方を間違えると「既得権益」になってしまうからである。
既得権益を壊すための仕組み
先程の例では、年上や車力が長いと言うだけで、ある特定の人が、責任以上の権利を持ってしまっています。つまり、「悪い権利」であり「既得権益」と化している状態です。
そのベテラン社員が権利を持っていたとしても、何が問題が生じたときに、責任を取れません。
「私は関係ありません。その新入社員の上司の責任です」と、言い逃れができてしまいます。こうした状況をなくしていくのが、人の上に立つ人の役割です。
先程の例であれば、上司がキッパリと、「私が許可したので、問題ありません」とベテラン社員に伝え、新入社員をも守らないといけません。
そして、全社員に向けて、「上司が許可したなら、他の社員に前もって了承もらう必要はありません」と明文化して伝えるのです。もし、ベテラン社員を尊重した方がチームのためだと判断したのであれば、「ただし新しく業界を変革するときに前の担当者が社内にいるのであれば、その人に事前に話を通すよう」にと追記して、ルールを決めれば良い。こうすると部下は迷いません。
そうやって既得権益を壊すために、仕組み化で解決することができるのです。
P83・84
このように指揮系統と権限を明確にし下っ端が迷わないように業務をこなすのが上司としての責務であるということなのだろう。

なかなか的を射ていて読んでいると「たしかにな」と思わせる文章に多く出くわしたのじゃ。
ま、お前は人の上に立ったことはないんだけどなw

そしてその他にも上司に必要なのは「怖い人」になるという話もなかなかおもしろい。
会社に入ったのなら成長しなくてはいけない。「安心感」ではなく「このままではマズい!」という危機感を持たせること、それができる人が「怖い人」であり、その「危機感」をうまく使うことによって部下を成長に導くことができるということ視点がとても面白いw

部下にいい意味でのプレッシャーを与えて成長を促すのが上司の努めなんじゃな。
その際にパワハラ的な勢いで恐怖を与えるんじゃなくて「このままの自分では会社に残れないんじゃないか」という「成長することを前提」にした、良い意味でのプレッシャーを与え続けてやることが重要なんだな。

どんな会社にも理念はある
そして最後に最も重要なのが自分が属している組織の「企業理念」はなんなのか?という点である。
70ページでも述べたようにビジョンやパーパスにと呼ばれる概念があります。どんな会社でも必ず創業者がいて、社会に向けて実現したい思いや、やむにやまれぬ動機があって、事業を起こします。
その際、作られるのが「企業理念」です。
「私たちの会社はものづくりで人々を豊かにします」
「私たちは地域ナンバーワンの建設現場を届けます」
「私たちの会社は世界中に食を届けていきます」
など、どんな会社にも企業理念があるはずです。
(中略)
しかし、「企業理念」と言うのはナメて扱われることが多いです。「理念」と言う言葉が説教臭いからでしょうか。
若い時は、そういうものを馬鹿にしているはずです。あるいは若手の頃はバリバリと働いていたのに、いつの間にか成長を諦めて、会社にしがみつき、企業理念のことなんて1秒たりとも考えることがない中堅社員、ベテラン社員もいるでしょう。
確かに、日々の仕事の中で、私たちの企業理念は〇〇だよねと確かめ合う事はないでしょう。
お互いに口にすることは恥ずかしいのかもしれません。
しかし、一人ひとりの社員の心の中には、常に企業理念があり続けるべきだと思います。その下に全社員が一堂に集まっているからです。
P201・202
一応、会社に入社したということはその企業の企業理念に共感して入社したはずである。
なので働くうえでやはり「企業理念」というものは忘れるものではなく、常に念頭に置いて日々の業務に勤しむべきだということだろう。

最初に抱いた「志」は忘れるなということかのう。
歯車は歯車でも「重要な歯車」
「属人化をなくして歯車のように働く」と言う事は、「社会に対して有益になる」と言うことです。あなたの存在が、誰かの役に立つのです。組織が大きくなるにつれ、たくさんの存在を獲得できます。
社会人は、代替可能です。
社長である私も、同じです。
私がいなくなっても、組織は回るでしょう。
しかし、今は役割があるから、それを果たしている。
それ以上でも、それ以下でもありません。
先ほども述べたように、「かけがえのない歯車」になりましょう。たとえ「歯車であっても、なくなったら困る歯車」だと周りが感じてくれるのであれば、それで充分です。
プレーヤーも、
マネージャーも、
組織のトップも、
会社にとって、一つ一つが重要な部品であるから、機械は大きな動きができる。
そう考えることだってできるのです。「属人化」と逆の方向を目指すことで、「あなたがいないと困る」と思われるような歯車になる。
逆説的に、「私らしさ」と同じ目的が果たされます。
組織のために働き、人の上役に立ち、
最後は組織の中で、辞めるのが惜しまれるというような人。
ぜひそれを目指してください。そのために、今の目の前の仕事に集中してください。仕事は別にある独人化の世界も大事にしてください。
それが、本書を読み通したあなたにお伝えする私からの最後の言葉です。
P306・307

勤めるということは自由も何もかもなくして血の気のない歯車になるものだと思っていたけど、そんな歯車にもそれなりの人生があるということなんじゃのう。
一見、替えの効く人材になるってことは人間性を失うことのように思えるけど、組織の一員になることによって個人ではできない大きなことができるようになるってのが、会社という組織の醍醐味なんだよな。


勤め人なんて退屈なもんじゃと思っていたが、これを読むと考えさせられる一冊であったのじゃ。
良いところ
では以下に良い点を挙げていこう!
一貫した実績に基づく信頼性
全国3500社以上に識学メソッドが導入されているという事実が、その普遍性と実効性を物語るnote(ノート)紀伊國屋書店。単なる理論ではなく現場で使われ続けている点が、本書への信頼感を高めている。
シンプルかつ読みやすい文体
著者の言葉は平易でインパクトがあり、読んでいて実践へのモチベーションが高まるとの声が多い短い雑記。複雑な組織運営論を日常語で解きほぐしている点が、読者層を広げている理由だろう。
シリーズとの流れによる思想的蓄積
『リーダーの仮面』『数値化の鬼』と一貫した流れの上で構成される完結編であり、組織成長に必要なリーダー思考を段階的に学べる構造が優れている100冊読書ブログ 読むねっこプレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES。

読みやすい点が本書のシリーズの魅力かのう?
まぁ、だいぶわかりやすい本ではあるよな。
少し行間が空きすぎている気がするけど、目からウロコだったぜ。

気になった方はこちらからどうぞ
悪いところ
では以下に悪い点を挙げていこう。
哲学的深みの欠如
あくまで実践型のマネジメント指南書であるがゆえに、理論的・哲学的な深掘りを求める読者には物足りない面もある。
新規性がやや薄れる可能性
シリーズ三部作完結編としての位置づけゆえ、先に前作を読んでいる読者には「再編」「再確認」の印象が強くなる恐れがある楽天レビュー。
抵抗や反発への対応への記載乏し
仕組みの導入には現場の反発がつきものだが、その具体的な乗り越え方や交渉方法についてはやや記述が限られる印象もあるnote(ノート)kt-kiyoshi.com。

読んでいて物足りない部分はもう少し具体例がアレばよかったのう。
説得力のある語り口で論理展開も見事なんだが、具体的な事例をもっと多く見たかったな。
そういう意味では少し書き方がクールだったな。


人によっては味気ないと感じるかもしれんな。
サクッと読めるのは本書の魅力の一つなんじゃが⋯⋯
まとめ
こんな人におすすめ!
- 属人化を防ぎ、組織基盤を強化したい管理職・リーダー
- 実績に裏づけられた思考法を短時間で習得したい人
- 具体的な導入事例に基づく実践書を求めるビジネスパーソン
『とにかく仕組み化』は、実績ある識学メソッドをベースに、組織を強くするための思考法をわかりやすく提示する実践書である。3500社以上導入、発売1ヶ月で22万部突破という数字が、その普遍的価値を裏付けているnote(ノート)Audible.co.jp。言葉はシンプルながら重みがあり、組織運営の現場において再現性ある指針を与えてくれる点が魅力だ。ただし、理論や哲学の深さを求める読者には浅く感じる可能性もある点は注意が必要。それでも、思考法として実践にすぐ結びつけたい人にとっては、即効性があり信頼できる一冊である。

組織を変えたいなら、まずは仕組みに目を向けるのじゃ。
人ではなくルールに頼るその思考こそ、真に強い組織を築く鍵となるのじゃ。







